〒231-0014 神奈川県横浜市中区常盤町3丁目24番地 サンビル8階
JR京浜東北線 関内駅北口(横浜駅より出口)から徒歩4分(横浜市営ブルーライン 関内駅3番口から徒歩2分)
後見人の選任申立て手続き
申立て手続き
成年後見人とは、判断能力が衰えたことにより、ご自身で金銭などの財産の管理、処分が難しくなってきた方を財産管理の面からサポートする法定代理人のことを言います。成年後見人は法定代理人ですので、家庭裁判所が選任します。
家庭裁判所が選任するためには、成年後見人を必要としている方が必要書類をそろえて選任の申立てをする必要があります。ご本人の財産に関する権限を代理人に渡すことになりますので、必要書類も多くなります。ご自身でも行うこともできますが、専門家に任せていただければスムーズに手続きを行うことができます。
具体的な申立て手続き
申立てできる方
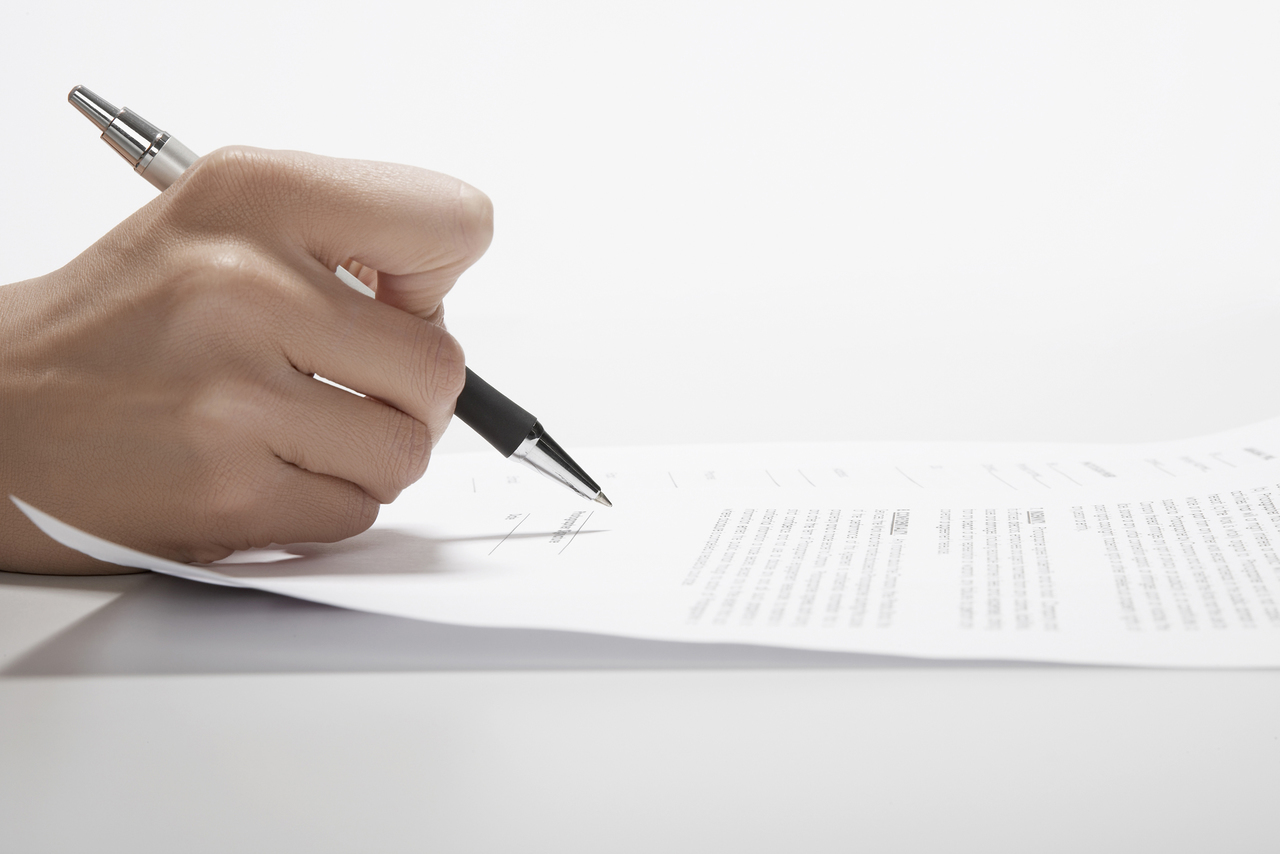
ご本人の権限に制約がかかるので、誰もが申立てをできるものではありません。申立人となることができるのは、ご本人、4親等内の親族です。その他に、申立てが必要だけれども申立人となる方がいない場合には、市町村長も申立てをすることができます。
申立人になりますと、申立手数料、診断書作成料などが基本的に申立人のご負担となり、申立書の作成を専門家に依頼するとこの専門家の報酬も申立人負担となります。
申立書類作成の手順
①診断書、本人情報シートの取得
まずは医師による診断書が必要になります。この診断書によってご本人が、どの程度の認知機能があるのかが判断でき、この結果に基づいて申立書を作成していきます。
診断書を作成するためには、担当のケアマネジャーの方などが本人情報シートを作成し、その本人情報シートをもとにして医師が診断書を作成します。本人情報シート、診断書は、様式が定まっていますので指定の様式を利用ください。
②必要書類の収集
ご本人の戸籍、住民票、登記されていないことの証明書、預金等の財産の調査、推定相続人の調査などの必要書類を収集します。
③後見人候補者の決定
後見人は家庭裁判所が決定しますが、親族や司法書士などの専門職を後見人候補者として申立書に記載することができます。ただ、候補者を記載したとしても、後見人を誰にするかは家庭裁判所が決めますので、候補者が後見人として選任されるかどうかは家庭裁判所の判断になります。
④推定相続人の同意書
推定相続人の方が、後見手続きをすること、後見人候補者について、それぞれ同意するのか、反対するのかなどを記載します。
⑤申立書の作成
申立書と以上の添付書類をつけて管轄の家庭裁判所に提出します。管轄は、被後見人となる方の住民票の住所地の家庭裁判所になります。
必要書類の収集
①戸籍、住民票の取得、推定相続人の調査
ご本人の現在戸籍、住民票(又は戸籍の附票)と併せて、推定相続人の調査のため、ご本人の生まれてから現在までの戸籍も一緒に取得すると手続きはスムーズです。戸籍は、現在は、ご本人や親族の方が戸籍を取得する場合には、本籍地以外の市区町村でも取得できるようになりました。
②登記されていないことの証明書
神奈川県内では、横浜地方法務局のみで取得することができます。法務局の中でもみなとみらい線の馬車道駅にある法務局だけで、他の法務局(支局、出張所)では取得できませんのでご注意ください。内容は、後見申立てをするにあたり、既にご本人に後見人が選任されていないことを確認するためのものです。
③ご本人の財産関係資料(すべて写しで大丈夫です。)
・預貯金 預金通帳
・不動産 登記事項証明書及び評価証明書
・株式等 証券会社からのお知らせ(銘柄、株式数などが分かるもの)
・自動車 車検証
・各種保険 保険証券 など
わかる範囲のもので大丈夫です。後見人が選任されてからしっかりと調べますので。
④後見人候補者がいる場合は、その方の資料
後見人候補者の事情説明書と住民票。事情説明書には、候補者の方の財産状況やご本人と候補者との関係などかなり詳しく記載することになります。
④ご本人の健康状態に関する資料の写し
介護保険証、療育手帳などをお持ちの場合には、写しを提出します。
申立書作成の注意点
申立書の作成のルールが家庭裁判所から示されていますので、そのルールに基づいて作成することが必要になります。
例:コピーは左側は3センチ以上空白を設ける、資料番号の振り方など
家庭裁判所への提出後の手続き
申立書の審査
家庭裁判所に提出後は、家庭裁判所で申立書の審査をして、添付書類はあるか、各書類と添付書類都の整合性、あるいは、各書類間の整合性などがチェックされると思います。そのうえで、資料の追加、修正、確認の連絡が入る場合があります。
書記官との面談

後見人候補者をご親族としている場合には、申立人、後見人候補者と家庭裁判所の書記官との面談が行われます。
面談では、後見人候補者が成年後見制度をしっかりと理解して、被後見人の財産管理がしっかりとなされるかを見ていると思います。
後見人となった場合には、後見人の指導、監督をするのは家庭裁判所が行うことになるからです。
提出後の注意事項
申立書を提出した後は、ご本人に後見手続きが必要なことに変わりはないため、申立書を取り下げすることはできなくなります。たまに聞くのが親族を後見人候補者として提出したのに、専門職が後見人になったので、取り下げしたいなどですが、この理由では絶対に取り下げはできませんのでご注意ください。
選任手続きの確定
関係者への特別送達等
家庭裁判所での手続きが終わると、後見人に特別送達がされるとともに、ご本人、申立人などにも通知されます。この通知に誰が後見人に選任されたかが記載されています。自分を後見人候補者にして特別送達が届かなければ、他の方が後見人に選任されたことになります。
後見人が確定するのはいつ?
後見人の選任の審判手続きが確定するのは、後見人に特別送達が届いた日から2週間経過すると確定します。この2週間は、関係者による不服申し立て期間になっています。この期間に家庭裁判所から何の連絡もなければ後見人の選任審判は確定します。
ここから法定代理人となり、ご本人に代わりにさまざまな手続きを行うことになります。
財産調査期間
後見人への特別送達の中には、いついつまでに財産調査等をして初回報告書を提出する日にちが定められています。多くの場合は、1か月から1か月半くらいの期間が定められています。
この期間に金融機関や行政機関に後見人の選任の届出を行うとともに、ご本人の財産状況の調査を行って、初回報告書を家庭裁判所に提出します。
いよいよ成年後見のスタート

初回報告をするまでは、後見人に選任されたとしても財産の維持管理権限しかなく、不動産の売却などの処分行為
を行うことはできません。
初回報告をして初めて法定代理人としての後見業務がスタートします。しかし、代理権があるからと言って何でも自分の判断で行うのではなく、ご本人と相談しながら進めるという意識を持ちながら後見業務を行うことが大切になってきます。
新着情報・お知らせ
「おひとりさまの手続き」のページを追加しました。
「はじめての後見人の手続き」のページを更新しました。
お気軽に
お問合せください

お電話でのお問合せ・相談予約
<受付時間>
9:00~18:00
※土、日、祝日は定休日
※予約で時間外定休日対応可
フォームは24時間受付中です。お気軽にご連絡ください。
司法書士星法務事務所

住所
〒231-0014
神奈川県横浜市中区常盤町3丁目24番地 サンビル8階
アクセス
JR 京浜東北線 関内駅北口(横浜駅より)から徒歩4分
横浜市営ブルーライン 関内駅3番口から徒歩2分
受付時間
9:00~18:00
※予約で時間外定休日対応可
定休日
土曜日、日曜日、祝日

